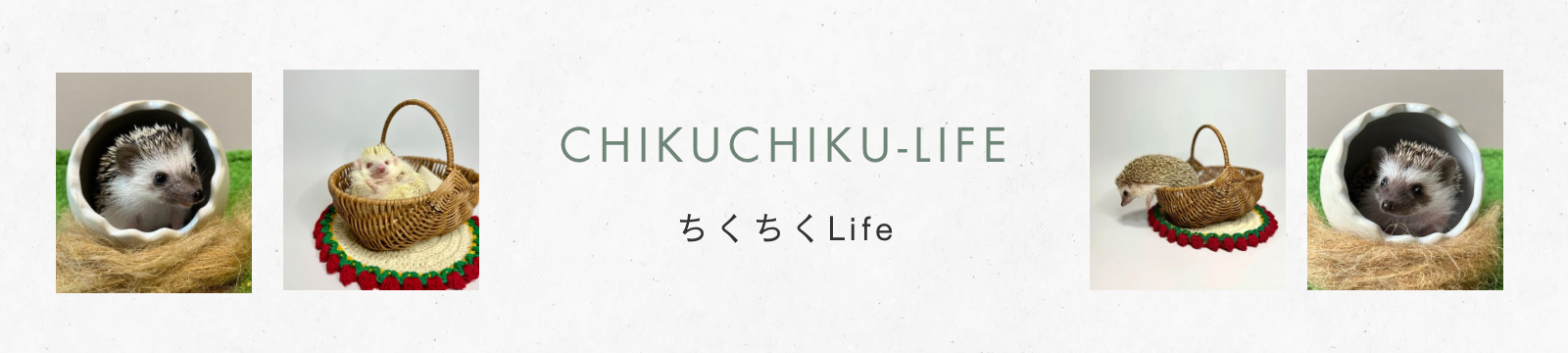ハリネズミの分類や特徴、ハリネズミの暮らしについて
まずお迎えする前に、ハリネズミのことを知りましょう。
理解を深めることで、今後の飼育にも必ず役立ちますよ
生物的分類やカラー
ハリネズミは以前、モグラやテンレックとともに「食虫目」に分類されていました。
どこかで「ハリネズミはモグラの仲間」と聞いたことがあるかもしれませんね。
現在では、分類が見直され「ハリネズミ目」に分類されています。
現在、日本で愛玩動物として飼育されているハリネズミは、アフリカに生息するヨツユビハリネズミという種です。
アフリカンヘッジホッグや、ピグミーヘッジホッグなどとも呼ばれています。
ハリネズミにはカラーのバリエーションがとても多く存在します。
筆者は飼育8年目ですが、正直カラーの見分け方については自信がありません。
全体の○%が何色で…と言われてもピンとこないからです。

カラーは100近くあると言われているよ
ハリネズミについて最も研究されているのは、ヨーロッパに生息しているナミハリネズミで、そのほかの種のハリネズミはあまりよく知られていません。
今では日本でもペットとして飼われることが多くなったヨツユビハリネズミが、野生化でどのような暮らしをしていたのかは、実はよくわかっていないのです。



一般的に犬や猫以外の愛玩動物は、エキゾチックアニマルと言われるよ
ハリネズミと法律
アフリカが生息地であるヨツユビハリネズミは外来生物ですが、特定外来生物に指定されていないため、日本で飼育することができます。
それは、暖かい地域に住むヨツユビハリネズミは、日本の冬を越せないと考えられているからです。
懐かないからという自分勝手な理由で、ハリネズミを外に捨てたらどうなるでしょう…
ハリネズミは飼い主を選ぶことができません。
動物愛護管理法でも、終生飼育は飼い主の責任として定められています。
可愛いから、映えるからと安易に飼うのではなく、ハリネズミの生態について十分に理解してからお迎えしてください。
ハリネズミは小さな動物ですが、命ある生き物だということ。
温度・湿度管理が重要で、医療費も意外とかかりますし、簡単に飼育できるわけではありません。
エアコンは1年中、湿度管理に加湿器も必須と言えるでしょう。
ハリネズミの特徴
筆者がハリネズミと暮らし始めてビックリした事と言えば、クイリングとアンティングです。
簡単に言うと、針の抜け替わり。
生後2週から6週ごろまでに、ベビーの針から大人の針へ。
6カ月頃まで、数回続きます。
筆者が初めてお迎えしたハリネズミのシェリーは、「ホワイトパイド」という白い針カラーでした。
4カ月でお迎えし、クイリング後はソルト&ペッパー(ノーマルカラー)に変わりました。カラーにこだわりはなく、この子がいい!とお迎えしたのですが、大きな変化でビックリしましたね。
他の子でそんなにもカラーが変わった子は、シェリー意外では出会ったことがありません。


クイリング前


クイリング後
クイリング中は、とてもストレスがかかる時期です。
触られてイライラする子もいるので、静かに落ち着いて過ごせるよう見守ってあげましょう。
匂いや味に反応して泡を作り、体を反りながら体に塗り付ける行動です。
この行動の原因や目的は、いまだに解明されていません。不思議ですよね。
アンティングという言葉は知っていたものの、実際に見たことがなかったので、とても動揺したのを映像で思い出せます。
何かに取りつかれたような…ただならぬ雰囲気で。
無意識に動物病院へ行く準備をしていました(笑)
急にモグモグさせてるな~を思ったら、アンティングの可能性が高いので動画を撮る準備をしましょう!
大人になるとアンティングをする機会が減るので、貴重な映像になりますよ


生後2か月頃のアンティング
生理学的特徴:外皮
ハリネズミの背中側を覆う針は、毛が変化したもの。
背中側の皮膚に皮脂腺はなく、顔の周辺やお腹側には汗腺や皮脂腺があります。
前足の指は、5本。後ろ足の指は4本しかないことから、ヨツユビハリネズミという名前の由来となっています。
皮脂腺
皮膚の内層にある器官で、皮脂を分泌する腺のこと。
肌のうるおいを守り、皮膚や毛の表面を保護します。
汗腺
汗を分泌する器官のこと。
汗は、体温調節やストレスなど色々な要因によって分泌されます。
消化器
歯は36本あり、歯と歯の間隔が広く、昆虫を食べるのに役立っています。
わかりやすく言うと、すきっ歯みたいな感じですね
しかし、飼育しているハリネズミにとって昆虫は、あくまでもオヤツで、普段の食事はハリネズミフードを主食とします。
ハリネズミは歯肉炎など、お口のトラブルは多いので、正常な状態を写真などに撮っておくと、あとあと確認しやすいです。
また、ハリネズミには盲腸がなく、消化管の通過時間は12~16時間と言われています。



人間は24~48時間で排出されるよ
チンチラなど嘔吐できない動物もいますが、ハリネズミは嘔吐することもできます。乗り物酔いをしたときに、胆汁の影響で緑色の嘔吐をしたりします。


生後1か月頃のあくび
泌尿器
左右の腎臓、尿管、膀胱、尿道からなります。
おしっこの色は、通常、無色~うすい黄色です。
尿は人間と同じくアンモニア臭がします。
ハリネズミの暮らし
ハリネズミは夜行性で、昼間は寝ていることが多く、飼い主さんが寝たらハウスから出てくる子も多いです。
活動時間のほとんどを、食べ物を探すために歩き回っていると言われています。
我が家のハリネズミ達は、筆者がハリネズミ部屋に入るとハウスから出てきて、ホイールをしてますよ!とアピールをしてきます。
【ホイールをしたら、おやつをあげる】ことを繰り返してきたためです。



私たち意外と覚えてるんだよ
飼育本やネットの情報だと、午後9時~0時が最も活発だと言われています。
我が家のハリネズミ達は、早い子は午後9時頃から活動を開始し、午前4時頃までホイールをしています。
1番長い子だと午前8時過ぎまで…



ハリネズミは単独生活をする動物だよ。
ケージは1匹に1つ用意してね!
針葉樹アレルギー
ハリネズミは、松(パイン)や杉、ヒノキなどの針葉樹にアレルギーを持つことが多いです。
症状としては、痒み・皮膚の赤み・脱毛・涙目・鼻水などがあります。
特に、ハムスター用の床材に多いパインチップなどは、針葉樹を使用したものが多いので注意が必要です。
また、ハウスも直接肌が触れるので、広葉樹の物を選びましょう。ハリネズミ用と記載があっても、販売者に知識がなくコーティングなしの針葉樹を使用している場合があるので、信用できるショップで購入することをオススメします。



木製の撮影小物にも注意が必要だね!
人間のハリネズミアレルギー
ハリネズミの針が触れると、痒みが出たり、発疹、くしゃみが出ることがあります。
しかしこれは、飼い始めなければわからないことです。筆者も全ハリネズミに対してアレルギーが出るわけではありませんが、痒みと発疹がでます。
アレルギー症状が軽い場合は、石鹸を付けてよく洗い、アルコール消毒をすると治まることがあります。(アルコール消毒をする場合は、ハリネズミがいない部屋で行いましょう)
筆者はアレルギーのお薬を処方してもらっていますが、身体の調子が悪い時に強くアレルギーが出ることが多いです。
アレルギー症状が強く、飼い続けられないという場合は、捨てたりせず里親さんを探してくださいね。命にかかわることです。誰も責めたりはしません。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
「小動物だから簡単に飼える」と思って欲しくないので、あえて少し難しいことも記載してみました。
次回は、お迎えする前に準備しておくべきアイテムを紹介します。